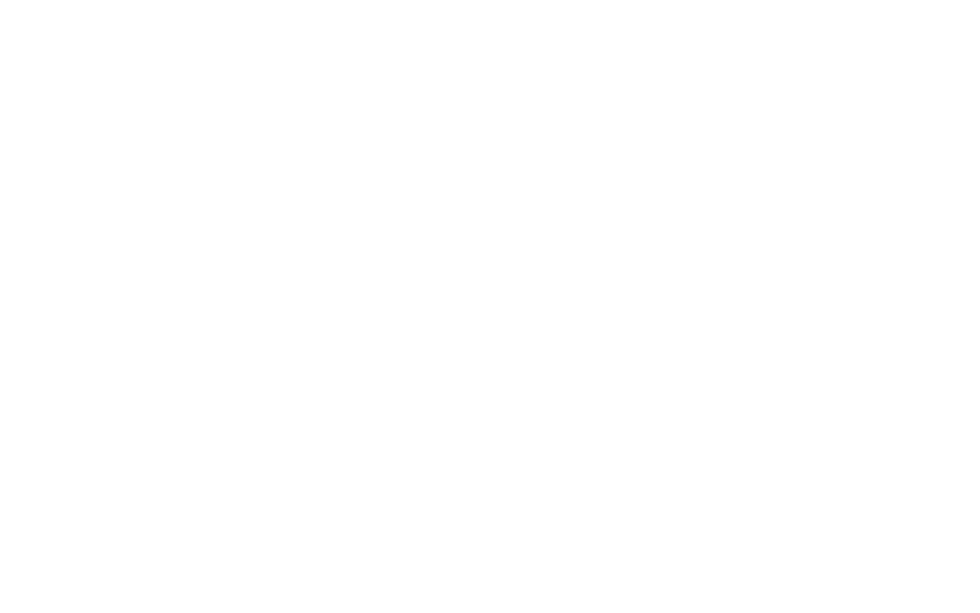地方創生における本来のビジネスの在り方
日米におけるまちづくりの考え方
木下さんが今のように地域の取り組みに関わるようになったのは1998年。東京の早稲田商店会で環境まちづくり事業に取り組んだことがきっかけだ。環境への取り組み意識が高まり始めた当時、木下さんは『エコサマーフェスティバル』を企画。商品アピールの機会が少なかった環境機器メーカーに出展料を払ってもらう代わりに、PRの場と早稲田大学教授陣による商品の機能性検証を提供。教授陣は検証結果を論文に書くことができ、商店会はメーカーの出展料により収入が得られるという仕組みをつくることで補助金なしでのイベント運営を可能にした。
「予算が少ない商店会だったので、こうして企画を考えてかかるお金を営業して集め、一つ一つのイベントを黒字にするのが当たり前だと思って活動していました。でもその後勉強のために全国の商店会を回ってみると、行く先々でみんな補助金の話をするんですよね。予算をもらって何かをするのが当たり前で、お金を自分たちで稼ぐ・もらってくるという意識がないことにすごく驚きました。早稲田の取り組みを真似ていた地域も予算が尽きるとみんな止めてしまって、補助金がもらえる次の話題の事業は何かということを一生懸命探し始める。これは根深い問題だと感じました」。
そして海外のまち会社を手伝った際に“まちづくりはアセットマネジメント(不動産経営)である”ということを認識させられたという。
「日本ではまちづくりは万人のための公共的な事業と考えられがちですが、アメリカでは違います。ある地域で何かをやるということはそこに必ず得をする人がいるわけで、その人たちが先行的に投資や負担をすることが問われる。この“負担者受益”という考え方が当たり前になっているため、アメリカでは“まちづくり=万人のため”という概念はありません。地権者を中心とした民間主導で事業を構築し、稼ぐ地域に変えていくことで成果を上げており、これこそがまちづくりの基本であるということを認識させられました。」
一方日本では、地域が赤字になった時に国による交付金を含めた“他人のお金”を使うため、万人に受けるまちづくりをしなければならないという現象が起きている。ところが万人のためにつくられたものは大して価値がないものにしかならないため、結局事業としてもうまくいかないという状況が続いているのだそうだ。
地方創生における本来のビジネスの在り方
木下 斉
一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事
1982年東京都生まれ。高校在学時からまちづくり事業に取り組み、00年に全国商店街による共同出資会社を設立、同年「IT革命」で新語流行語大賞を受賞。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。08年に設立した熊本城東マネジメント株式会社をはじめ全国各地のまちづくり会社役員を兼務し、09年には全国各地の事業型まちづくり組織の連携と政策提言を行うために一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンスを設立。全国各地の地域再生会社への出資、役員を務める。著書『まちづくり幻想』『稼ぐまちが地方を変える』『凡人のための地域再生入門』『地方創生大全』等多数。
OTHER ARTICLE
このカテゴリの他の記事